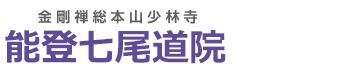2021-11-6 法話 「自信と勇気と行動力」
対象:年長、小学生、中学生、一般
少林寺拳法の目的は、自信と勇気と行動力を持った人間を育てる事だと副読本の中に書いてあります。昇級試験にも出てきていましたね。
「自信と勇気と行動力」の最初にある「自信」を身につけるには、どうしたら良いのでしょうか?
「自信」を身につけるには、小さなチャレンジを行い、その小さな成功体験が大切なのではないかと思います。「帯を自分で結べるようになった」でも良いし「昇級試験に合格した」「この技ができた」でも良いと思います。小さな成功体験の繰り返しと、「頑張ったね」「良かったね」と言ってもらえる承認体験が重要なのだと思います。
この小さな自信があると、初めての事でも挑戦してみようと勇気が湧いてきます。この小さな勇気があると行動に移すことも出来ます。例え、行動した結果が失敗しても、もう一度チャレンジしてみようとなります。または、別の方法を試してみようと切り替えることができます。
この話をしたのは、練習前に「ほら、帯を自分で結んできたよ」見せに来てくれたからです。「おう、すばらしい」「やったね」
小さな成功体験は何でも良いと思うのですが、せっかく少林寺拳法を修業しているのだから少林寺拳法を通して自信を持ってもらいたいと思います。
——————-以下は補足です——————
自分を信じると書いて「自信」といいますが、「自信」とは何でしょうか?
「自信」は、「自己肯定感」と言い換えることができるかもしれません。
「自分はできるんだ」と考えられるかどうか?
チャレンジして成功できれば一番良いのですが、例え失敗しても「自分は大丈夫」「もう一度チャレンジすれば良い」と考えられるか?または、「他の可能性がある」と考えられるか?なのでは無いでしょうか?
「自信」を身につけるには、小さなチャレンジを行い、その小さな成功体験が大切なのではないかと思います。小さな成功体験の繰り返しと、身近な人から褒められた承認体験が重要なのだと思います。
「自信」が無いと他人や社会から必要とされていないと感じ、他人や社会から疎外されていると感じてしまいます。これが内向きに強く働いてしまうと、「鬱」や「閉じこもり」となってしまい、周りからの情報・刺激に反応できなくなったり、遮断してしまったりするのだと思います。また、自信が無いけどプライドは傷つけられたくないと感じると、外向きに攻撃性が強く働いて、切れやすくなったり、他人を傷つけたり、犯罪に走ったりするのだと思います。これも周りからの情報・刺激に過剰反応しているのだと思います。
もしかしたら、実力が無いのに自信過剰の人も、実は「自信」が無いので過剰に認められたいと思っていて、知らない間に虚勢を張っているのでしょうか?
「小さな自信」が沢山貯まっている人は、「心的エネルギー」が満ちてる人だと思います。
「心的エネルギー」満ちているからこそ、他人にも良い影響を与えることも出来るのだと思います。本当の意味での「自信」を持って、他人も良い影響を与えれる人が、「自信と勇気と行動力を持った人間」と言えるのでは無いでしょうか。