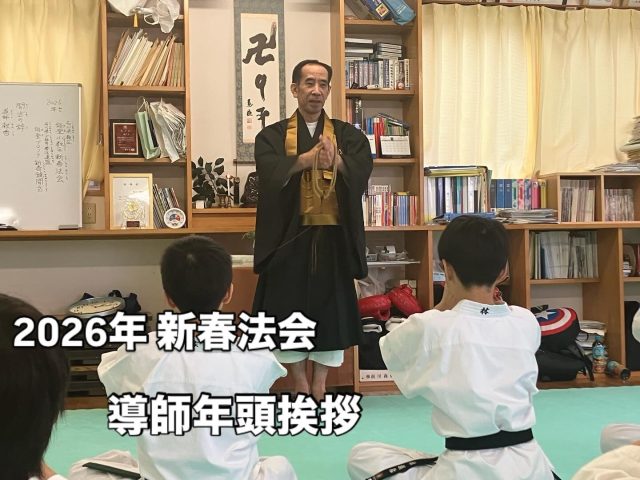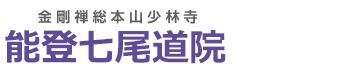2024年11月28日(木)法話 鎮魂行について
*鎮魂行中に少年拳士がサワサワと落ち着きが無かったので、鎮魂行後の法話で、2024-10-20 日本武道館主催 令和6年 石川県地域社会少林寺拳法指導者研修会 坂下 充 先生の講義の中の鎮魂行のお話を少し自分なりにアレンジしてお話しを行いました
皆さんは、少林寺拳法の練習をしに来ているんですよね? 頷く少年拳士(多分、鎮魂行中にモゾモゾ動いていたことを叱られると思ったのか、身構えている)を見回してから
実は、チョット違うのですね〜
皆さんは、ここに修行に来ているのです(うん、うんと頷く子と おや?という顔の子もいます)
少林寺拳法を練習することを通して、一の手段として、修行しているのです
少林寺拳法の練習は、一つの手段です
練習前には、作務もあるし、鎮魂行もあるし、これら全てが修行の内です
サッカーの練習や野球の練習などは、試合に勝つために一生懸命に練習しますよね?
少林寺拳法の練習は、それとは少し違うのですよね!
何度かお話ししたことがあったと思いますが、少林寺拳法の修練を通して、カラダとココロを強くするのが目的、目指すのですよね
つまり、皆さんは、修行しているのです
この鎮魂行も修行の一環で、実は、教典を唱和しているとき、こんなストーリーがあるのです
先ず、道院の玄関先で、「修行したいのですが?」と尋ねてくる人がいたとします
道院長が、「あなたは、どの様な修行がしたいのですか?」と質問します
すると、教典の中の”聖句” 「己こそ己のよるべ・・・」と答えます
道院長が、分かりました では、お入りください
道院長が、「では、この道院での決まり事をお伝えします」「守って頂きます」と”誓願”を唱和します
道院長、「では座禅を組みましょう」と着座、安座して姿勢を整えます
道院長、「座禅行を行う上で大切な事をお伝えします」”礼拝詞”を唱和
道院長、「これは、自分の可能性を信じて修行していくことを意思表明するものです」
道院長、「正しくこの修行を行っていけば、次の事柄が日常生活の中で達成されていきます」”道訓”を唱和
しばらく、座禅行、瞑想をして(ある程度の長さの時間が必要)
バシン と打棒の音がして、「起立」の号令
道院長が修行者の方を向いて対面し、”信条”を唱和
これは、同じ修行者の仲間同士が、修行を継続するために、挫けそうになる自分を鼓舞するため、お互いに誓いや目標を表明している
この様な事を毎回、道院に来たときに行っているんですよ!
毎回、今から修行するぞ!とお互いに誓い合っています
鎮魂行の時間も大切したいと思います どうですか?
*実際に話した内容とは、少し言い回しなどは違うかもしれませんが、だいたいこの様な内容で法話を行いました